 
第3話(その3)
「どうせ人を殺すのなら、理由がないよりもあったほうがましだろう。そのために、国のお偉方は、戦争に聖戦だとか正統な権利の回復などとたいそうな名前をつけて、おれ達を戦場に送っているんだ」
千年帝国軍要塞「バルディアスの門」を構成する三つの要塞の一つ「スクルド」の士官室で、エンリーク・ソロは友人のアイスマン大佐に熱っぽく語っていた。アイスマンは彼の士官学校時代の同期生で、現在、神将タイラーの副官を務める優秀な男である。まだエンリークが、ベルブロンツァ会戦の敗戦で大佐に降格される以前の、階級が異なるときにも、同格の立場で会話ができる仲だった。
「お国の批判か?ほどほどにしておいた方がいいぞ。ただでさえ、お前は目をつけられているんだからな」
アイスマンは友人の身を案じて忠告した。
「文句のひとつも言いたくなるさ。自分たちはぬくぬくと安全な場所にこもって、おれたちに戦え戦えと前線に送り付ける。それに、戦いに負けたら、敗戦の責任のすべてを前線の将兵に負わせようとするんだからな。まともな奴なら、やってられないよ」
エンリークは密かに持ち込んだアルコールをコーヒーに入れて一気にのどに注いだ。
「気の毒だったな。将官にまで出世しながら逆戻りなんて。上官のめぐりあわせが悪かったとしか言いようがない」
「アイスマン、同情はいらんぞ。おれは別に後悔しているわけじゃないからな。ただ、世の中の面白くないことに文句を言ってるだけだ。そこのところを理解しておいてくれよ」
「あいかわらず、正直な奴だ」
時の経つのも早いもので、ベルブロンツァ会戦からすでに五ヵ月が経過している。その間、エンリークは一ヵ月間、本国で謹慎し、四ヵ月間は再びバルディアス方面軍に呼び戻されて、壊滅させられた第三二艦隊の残存部隊とともに、タイラーの直接指揮する第七艦隊に編入されていた。艦隊幕僚補佐というのが彼の身分であった。
ここ数か月、「バルディアスの門」を守備する帝国艦隊は、戦いらしい戦いを経験していない。クレティナスの侵攻に備えて、未だ一四○○隻の艦隊が駐留しているのだが、食料と人件費の無駄な消費を続けていた。仕事といっても、たまに付近に出没する「暗黒の牙」とかいう宇宙海賊を追うくらいで、艦隊が出撃するようなことはなかった。
「暇なのもいいが、たまには腕をみがかないとせっかくの才能も錆付くというものだ」
これは、副官であるアイスマンにこぼしたタイラーの言葉である。神将と呼ばれるタイラーは、決して武を愛し文を軽んじる軍人肌の人間ではなかったが、暇な平和の時間が長く続くと、やることを失って、何となく戦いがなつかしいものに感じられるのだった。
ユークリッド・タイラーは宇宙標準暦一五二九年生れの青年で、千年帝国では男爵という貴族の称号を持っている。エンリークやアイスマンと違って支配者階級に属す人間である。しかし、彼の人間性は、出身や門地にとらわれることがなく、能力のある者なら誰に対しても敬意をもって応じることができた。それゆえに、帝国首脳部からの信頼ばかりでなく、彼は部下や市民階級出の将兵からも絶大な人気を集めていた。貴族の嫌いなエンリーク・ソロにとってタイラーだけは別格であった。
エンリークはタイラーの執務室に呼ばれた。先日、帝国軍情報部にもたらされたクレティナス側の情報に興味深いものがあったので、彼の意見を聞いてみたいというのだった。
部屋に通されてすぐに、エンリークは数枚の報告書を提示された。
「目を通して君の意見を聞かせてくれ」
報告書を手にしたエンリークはぱらぱらとめくって声をあげた。
「自由艦隊ですか。クレティナス軍も面白いことをやりますなあ」
「その司令官にあの『赤の飛龍』が決まったそうだ」
エンリークはその名前に特別な響きを感じた。
「アルフリート・クライン少将……」
「いや、先の会戦の功績で中将に昇進したらしい」
先の会戦とはベルブロンツァ会戦のことである。これには、エンリークはもちろんタイラーも大きな借りがある。少数の艦隊によって、むざむざと一個艦隊を壊滅させられたのだ。帝国にとってはクレティナスに対する初めての敗北であった。
「彼に作戦行動の自由が許されたとなると、また、バルディアスが戦場になるのも遠くはありませんね。きっと近いうちにここまで遠征してきますよ」
「君もそう思うか。噂では、すでにフェリザールを発進したとも聞いているが、どこに向ったかは明らかになっていない。おそらく、彼はここに向っているのだろうが」
エンリークとタイラーは同様の意見を持っていた。二人がアルフリートの思考や性格を知っていたわけではないが、軍人としての直感がそう告げていたのである。
しかし、アルフリートが攻めてくるとわかっていても、タイラーは特別な対応策をとることはできなかった。敵がいつ到来するのか、どのような作戦を用いてくるのか、全く不明なのだった。要塞防御という任務がある以上、彼の行動の自由は、アルフリートほど広く認められていない。相手の出方を待って、それに応じた作戦をとることしか、今のタイラーにはできなかった。
「とりあえず、哨戒行動の強化と索敵衛星の設置くらいしかできないでしょう。あとは、いつでも艦隊が出撃できるよう待機させておくしかありませんね」
エンリークの出した結論にはタイラーもうなずくしかなかった。
アルフリート・クラインの勇名は、ベルブロンツァ以来、帝国軍の将兵たちのなかに浸透している。タイラーには及ばなかったが、軍首脳部から高い評価を受けていたヴァルソ・カルソリー中将の敗死は、今までクレティナスに脅威を感じていなかった将兵たちに、再認識の必要を迫るものとなった。
「敵の過大評価は、戦闘の士気の低下につながりかねないことであり、正常な判断を損なわせる原因にもなる。常に冷静に考え、自分の力を信じて敵に臨まなくては、勝てる戦いも勝てなくなるというものだ。君はもう少し、自分に自信を持った方がいい」
士官学校時代の恩師に受けた言葉を思い出して、エンリーク・ソロは苦笑した。決して敵が恐ろしいなどと思ったことはない。ただ、どんな敵にも細心の注意を払い、あらかじめ最悪の場合について考えておくだけのことなのだ。しかし、エンリークは不吉な予感を感じずにはいられなかった。ベルブロンツァの会戦の時にも、彼の予感はあたっている。エンリークは次に来るだろう戦いの敵が、アルフリート・クラインと予見して、一抹の不安を抱いていた。
結局、エンリーク・ソロの予感は、この後に行なわれることになったバルディアス会戦で現実のものとなる。「神将」と「赤の飛龍」を戦わせたらどちらが勝つかという命題が一つの結論を出すことになるのである。ところが、それが、後の新しき時代の始まりを呼ぶものであり、彼の人生を大きく変えていくことになろうとは、彼自身も想像することができなかった。
そして、宇宙標準暦一五六三年一月二二日、アルフリート・クライン率いるクレティナス軍とユークリッド・タイラー率いる千年帝国軍が、この年、最初の砲火を交じえることになる。いよいよ、運命の三姉妹の名を持つ「ウルド・ベルダンディ・スクルド」の三要塞の崩壊によって、人類社会の壮大な「ラグナロック(神々の黄昏)」が始まろうとしているのだった。
|
 |
  |
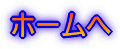
|

